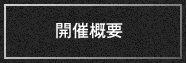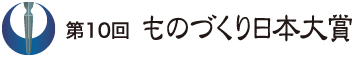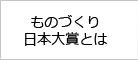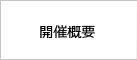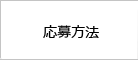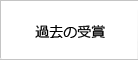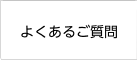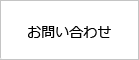■審査・選定方法
有識者で構成される選考分科会と選考有識者会議を設置し、第1次審査と第2次審査による選考を経て、受賞者の選定を行います。第1次審査を通過し、第2次審査に推薦された方は、別途追加資料の作成をお願いする場合がございます。
(1)第1次審査
選考分科会を全国9ブロック(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄)に設置し、応募があった担当都道府県内の候補者について審査し、第1次審査通過者を選定します。第1次審査では、応募書類による審査の他、必要に応じてヒアリングや現地調査による審査も実施します。
(2)第2次審査
第1次審査通過者について、選考有識者会議が第2次審査を行い、内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、特別賞、優秀賞について受賞者を選定します。第2次審査では応募書類による審査の他、必要に応じて現地調査及びプレゼンテーション等による審査を実施します。
※プレゼンテーション等の際の会場までの交通費等は出席者にてご負担いただきます。
■審査の基準
審査は「(1)![]() 製造・生産プロセス部門」、「(1)
製造・生産プロセス部門」、「(1)![]() 製品・技術開発部門」、「(1)
製品・技術開発部門」、「(1)![]() 伝統技術の応用部門」、「(1)
伝統技術の応用部門」、「(1)![]() データ利活用による新価値創出部門」、「(4)
データ利活用による新価値創出部門」、「(4) 人材育成支援部門」の5部門それぞれの受賞者を選定するために行います。各部門の審査・選考には、次の評価項目を総合的に勘案して行います。
人材育成支援部門」の5部門それぞれの受賞者を選定するために行います。各部門の審査・選考には、次の評価項目を総合的に勘案して行います。
(1)産業・社会を支えるものづくり
| 評価項目 | 評価内容(例) |
|---|---|
| a. 社会的課題への対応 | 技術的革新性だけでなく、モノに留まらないサービス・ソリューション提供や、人材不足をはじめとする社会的課題の解決を通じて新たな付加価値を創出している、もしくはその見込みがある取組を評価 |
| b. 革新性 | 新規性、独創性、新規市場の開拓可能性や、克服技術の難易度、ボトルネック解消の困難性、性能、品質面の優位性・信頼性、効率性、生産性、合理性、能率向上への寄与の面から評価 |
| c. 波及効果 | 経営貢献度(売上・収益、コスト削減)、市場シェア、新規市場への影響、他事業への転用・応用・将来性、普及可能性、既存システムへの影響の面から評価 |
(4)ものづくりの将来を担う高度な技術・技能(③人材育成支援部門)
| 評価項目 | 評価内容(例) |
|---|---|
| a. 社会的課題への対応 | 社会環境の変化を踏まえ、モノに留まらないサービス・ソリューション全体を考えられる人材の育成を通じて、社会的課題を解決している、もしくはその見込みがある取組を評価 |
| b. 革新性 | 新規性、独創性、類似する取組の有無、将来を担う人材がものづくりに対して興味を抱くような創意工夫、学校における学習科目との整合性、地域の関係機関との効果的な連携の面から評価 |
| c. 波及効果 | 自社に留まらず社会・地域で幅広く活躍する人材育成支援、取組の継続性、内容や参加人数の拡大可能性の面から評価 |